2023年のワールドベースボールクラシック(WBC)で見事世界一に導いた栗山英樹監督。
栗山監督は野球ノートをつけており、日ハムの監督時代にまとめたものが「栗山ノート」、そして2021年のWBCついてまとめたものが「栗山ノート2」です。
今回は、日ハム時代の「栗山ノート」の学んだことを3点紹介します。
「栗山ノート」の特徴は『四書五経』などの古典、経営者の著書から抜き出した言葉をよく引用しています。
たくさんの書籍を読まれており、そこから得たものを自分や選手に活かそうとするのが栗山さんのスタイルです。
「栗山ノート」の名言から学んだことを3点紹介すると、
①相手に我慢させない
②常識を疑う
③成功していない組織は部下を大切にしていない
の3点になります。
相手に我慢させない
何事にも動じない心の強さを持ちたい、と願っています。
しかし、実際にはなかなかそうもいきません。日常の様々な場面に、心がぐらつく原因が潜んでいます。
引用:栗山ノート(第1章 泰然と)
自分は一生懸命やっているのに、なぜ相手は答えてくれない。
このような状況に立たされると私たちは冷静さ保つことが難しくなります。
栗山さんは、「なぜ・・・・」という疑問を抱くより前に、相手の立場になるように心がけています。
「なぜ・・・・」と眉間にしわを寄せてしまうと、相手が心を閉ざしてしまうからです。
『泰然』は、落ち着いていて物事に驚かないさまや動じないさまを意味します。
栗山さんが考える『泰然』は、相手に我慢させないことです。
私の考える「泰然」とは、相手に我慢させないことです。意思表示の鍵を開けるために、力関係を形にしないように気をつけています。
引用:栗山ノート(第1章 泰然と)

僕は『力関係を形にしない』がとても腑に落ちました。
僕自身子供が2人いますが、どうしても子どもや後輩に力関係を形にしてしまう時があります。
栗山さんが考える人間関係で軋轢を生じさせないためには、
- 嘘をつかない
- 欲に走らない
- 相手の気持ちを考える
- 飽くことなく続ける
当たり前の行動をする。
自分ではなく周りの人たちの利益を最優先にする。
そうすれば、何事にも動じない心が宿ると考えているそうです。
常識を疑う
私がためらいたくないのは、「常識を疑う」ことです。
何か新しいものを生み出すには、セオリーや定石といったものにとらわれない発想が必要です。
引用:栗山ノート(第3章 ためらわず)
ルールを守らない、社会人としての規律から逸脱するようなことではありません。
先入観に引っ張られることなく、人を生かす、組織を生かす、組織を生かす、少しはためになるといったことです。
栗山さんは、2019年のシーズンに、オープナーと呼ばれる戦術を取り入れました。
これは、本来はリリーフで起用する投手を先発で使い、1,2回の短いイニングを任せた後に先発投手がロングリリーフとして投げるものです。
オープナー戦術は「先発投手の層の薄さを補うもの」と考えられていますが、栗山さんは「先制される確率を抑えるため」と考えました。
「無謀だ」とはっきり言われることもあったそうです。
- 目前の試合に勝つ確率を1%でもあげる
- 野球の可能性を掘り起こしたい
オープナー戦術にはこのような思いがありました。
セオリーや定石、常識といったものにとらわれず、新しいものを生み出していきたいのです。
その過程で批判を受けても、気にしません。坂本龍馬も批判の理由を誰かに押し付けたり、誰かを責めたりしなかった。まずは我が身を省みて、問題点をあぶりだした。そして、精進を重ねていったのでは、と思います。
周囲からどう評価されているのか、という不安や心配から自ら解き放って、自分の想念を「無の境地」に置く。そうすると、問題の所在がよく見えるようになります。
引用:栗山ノート(第3章 ためらわず)
成功していない組織は部下を大切にしていない
部下を大切にしていない
僕が自分の会社で最近良く感じていることです。
栗山さんは、古代中国の兵法書に『六韜三略』(りくとうさんりゃく)の『三略』にある
夫(そ)れ主将の方は、務めて英雄の心を攬(と)り友好を賞禄(しょうろく)し、志を衆に通ず
という言葉を引用しています。
これは、組織を引っ張っていく者は、部下の心をつかみ、部下の功績を称賛し、自らの志を組織に広く浸透させていかなければならないというものです。
成功をつかめない組織を分析すると、上司が部下を大切にしていないケースがきわめて多い。収益が上がっても部下の給料を上げない、自分だけ休んで部下を働かせるといったように、部下を冷遇しているのです。
上司が部下を冷遇するのは、自分の地位、名誉、財産といったものを守りたい、増やしたいと考えてるからでしょう。けれど、上司となった人も、仕事を始めたばかりのころは分からないことだらけで、ただひたすらに汗を流していたはずです。
引用:栗山ノート(第4章 信じ抜く)
野球選手にも様々な事情があります。
翌シーズンの年棒がダウンしたり、他チームへ移籍することになったり、現役を引退したり・・・・
刹那の世界で生きている野球選手は、我々サラリーマンより遥かに厳しい環境です。
でも、こんな時に忘れていけないのは『初心』だと栗山さんは言います。
初心を忘れてほしくないし、うまくいかないこともすべて受け止めて野球をやり切ってほしい。70人前後の選手にそういった気持ちを抱いてほしいのですが、個々の成長はとてもゆっくりしたものです。
引用:栗山ノート(第4章 信じ抜く)
監督に必要なのは忍耐
2019年清宮幸太郎選手が32打席無安打という時期がありました。
しかし、清宮選手は調子が上向かなくても必死に練習に取り組み、「なかなか結果が出ないこの時期をどう生かすかは自分次第です」とも話していたそうです。
栗山さんは、監督という立場でこのように考えていました。
だとすれば、監督に必要なのは忍耐です。幸太郎を信頼して使う。先発で起用しないこともありますし、先発で使っても代打を送ることもある。けれど、彼の結果に対してジタバタしない。あたふたもしません。
自分の身を正して、心を正して、清く正しく生活していく。愚直な積み重ねこそが、周りの人たちに響くのだと信じます。
引用:栗山ノート(第4章 信じ抜く)
まとめ、書評
以上、「栗山ノート」の名言から学んだことを、
①相手に我慢させない
②常識を疑う
③成功していない組織は部下を大切にしていない
の3点を紹介しました。
僕より遥かに本を読まれている栗山さんだからこそ、心に響く言葉です。
同時に、監督に必要なのは『コミュニケーション』と『常識を疑う』ことだと感じました。
栗山さんのような上司に出会いたいと願うばかりですがそううまくはいきません。
だけど、我々には「栗山ノート」がある。
自分の会社人生の道しるべとしてこの1冊を大切にしていきたいと思っています。
最後までご覧いただきありがとうございました!
※追記
「栗山ノート」の続編、「栗山ノート2」も紹介しています!

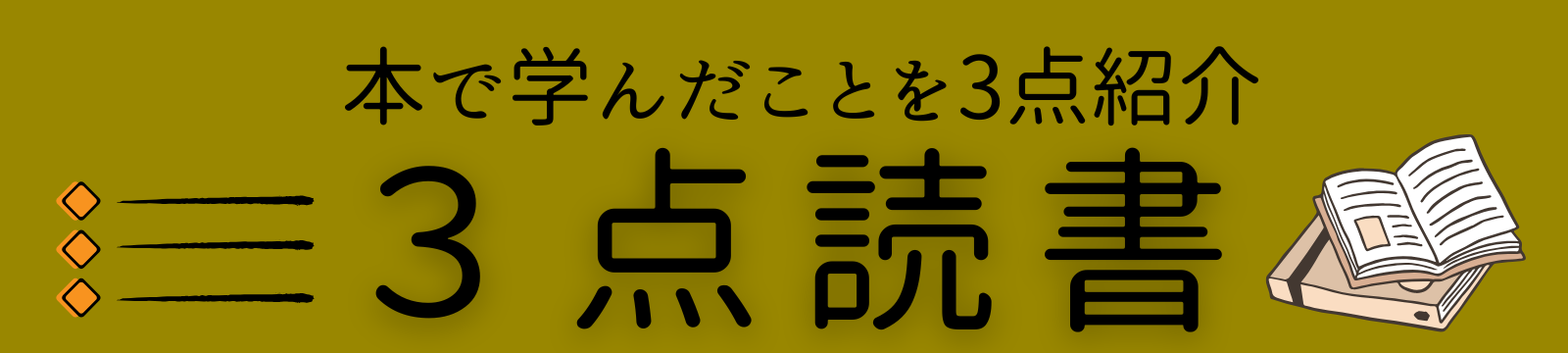

コメント