なぜ人間は正しくお金を使えないのか?
メンタリストDaigoさんも絶賛した「MIND OVER MONEY 193の心理研究でわかったお金に支配されない13の真実」から学んだことを3点紹介します。

僕もこの本を読むきっかけになったのはメンタリストDaigoさんの動画です!
実際にお金の使い方が大きく変わりました!
お金に対する思考には、実は様々な人間の行動心理が関わっています。
この本を読めば、その行動心理に惑わされにくくなります。
「MIND OVER MONEY 193の心理研究でわかったお金に支配されない13の真実」から学んだことを3点紹介すると、
①現金よりクレジットカードの方が多く支払ってしまう
②お買い得が脳をパンクさせる
③お金が貯まる心の持ち方
の3点になります。
現金よりクレジットカードの方が多く支払ってしまう
意外でも何でもないが、買い物金額が大きい時はカードを使うことが多くなる。そうすれば大金を持ち歩かなくてもいいし、しかもクレジットカードの場合は、まだ自分の物でないお金まで使うことができる。だが理由はそれだけではない。
カードを使うと、買う決心をしやすくなるだけでなく、思考が変わる。いくら払ったか覚えていないことが多くなり、チップを弾みやすくなる。しかも次に紹介する実験が示す通り、同じ品にもっと出していいと思うようになる。
引用:MIND OVER MONEY 193の心理研究でわかったお金に支配されない13の真実(Chapter2 カードはお金に関する捉え方を変える)
次に紹介する実験とは、
ボストンにあるマサチューセッツ工科大学のMBAコースの学生たちが、「心理学の実験に参加してもらえれば、その中から1名様にゲームの1週間前にペア・チケットを一組差し上げます」というもの。
チケットは地元のバスケットチーム(ボルトン・セルティックス)のシーズン最終ゲームで、地区優勝するためには勝つしかない大事な試合。つまりお宝チケットでした。
ただし、当確者はチケットの額面を支払います。学生たちはサイレント・オークション方式で競り落とした人の勝ちと聞かされています。
半数は現金払い、もう半数はクレジットカード払いです。
研究者は、
- お宝チケットに学生がいくらまで出そうとするか?
- とくに支払方法によって差が出るか
に注目していました。
結果は驚くほどの差でした。
- 現金グループの掲示額は平均28ドル
- カードグルプの掲示額は平均60ドル
まで出すという回答でした。
これには、このような人の行動心理が読み取れます。
現金で払った方が、どういうわけかずっと現実味があるし、お金が手を離れる痛みもずっと大きい。カードで払うと痛みは後から来て、購入が楽になる。なりすぎる人もいる。
引用:MIND OVER MONEY 193の心理研究でわかったお金に支配されない13の真実(Chapter2 カードはお金に関する捉え方を変える)

僕自身、30代前半まで超浪費家でした。
この本を読んで、その原因がクレジットカードを使っていたことに気づき、クレジットカードを固定費以外使わなくなりました。
クレジットカードとうまくつきあう方法は、
クレジットカードで何かを買うとき、ATMで同じ金額を引き出すところを想像する。そして、キャッシュで支払ってもいいと思えるときだけカードで支払うようにする。

僕は不器用なので、想像しながら支払うより、強制的に現金や前払いができるデビットカード、PayPayなどを使っています。
お買い得が脳をパンクさせる
人間は買い物の金額が大きくなるほど、それに付随するコストに無頓着になりやすいことが調査から分かっている。
引用:MIND OVER MONEY 193の心理研究でわかったお金に支配されない13の真実(Chapter3 心の会計と銀行の会計)
休暇で海辺に来ているとします。
海沿いをサイクリングしようと思い立ち、レンタル料金を見て回ります。
最初に入った店は3500円でした。
2つ目の店は歩いて10分かかりますが1400円でした。
差額は2100円です。

この場合、徒歩10分かかっても1400円を選ぶ人がほとんどだと思います。
今度は家に帰って、新車を買いに行きます。
最初に入ったショールームでは、気に入った車は1台140万1400円でした。
値段に納得したくて、10分歩いて別のショールームに入ります。そこでは1台140万3500円でした。
こちらも差額は2100円です。
この場合、2100円を惜しんで最初の店に戻ろうと思いますか?

レンタサイクルの時は2100円得して嬉しいのに、車を買うときは2100円なんて別にいいやと思ってしまう人がほとんとではないでしょうか?
本当に人間の行動心理って不思議ですよね・・・
意思決定において複雑にする要因が「割引」です。
- 2800円の花瓶が1400円割引(50%割引)
- 7000円の花瓶が1400円割引(20%割引)
この場合、2800円の花瓶の方がずっとお買い得だと感じます。
割引を見る前までは、7000円の花瓶を気に入っていました。
だが、節約できるお金は同額で、本来、50%割引に意味があるのは、2800円の花瓶を気に入っている時です。

先ほどのレンタサイクルと新車についても、人は頭の中でどれくらい割引かを判断するため、差額が同じ2100円でも判断が全く違うんですね!
お買い得に関して正しい判断をするためのヒントは、
割引がパーセントで表示されている時は、ちゃんと計算して金額を把握する。
お金が貯まる心の持ち方
認知心理学の実験結果によると、人は膨大な情報を扱う時、しかもデータがあいまいな時、判断を間違いやすくなる。しかも自分にとって都合のよい判断を下す傾向がある。
引用:MIND OVER MONEY 193の心理研究でわかったお金に支配されない13の真実(Chapter12 なぜ、お金が貯まらない?)
お金の話で言えば、貯金をいくつもの金融商品に分散(年金プラン、個人貯蓄口座、国債など)全部でいくらになるのか把握しておくのは難しいです。
人は自分にとって良い判断を下す傾向があります。
自分の資産も多めに見積もってしまい、これくらいなら使っていいと判断し、貯金する機会を失ってしまうのです。

本では、学生への実験で、貯金口座3つより1つの口座の方が残高が6%高かった実験を紹介しています。
日本の場合、ペイオフが1000万円までなので、1000万円以上預金がある場合は、口座を分けるのがおススメです。
マネーフォワードなどのアプリで把握できるようにするのもいいですね!
10年を3652日と言い換える
人は自分にどのくらい時間があるかを過大評価する傾向があります。
人は今の今までろくに貯金できなかったのに、これからはできると思う傾向がある。
将来はきっと収入が増えるし、もっと貯まるはずと考える。
引用:MIND OVER MONEY 193の心理研究でわかったお金に支配されない13の真実(Chapter12 貯める時間)
このような行動心理に対して、「時間枠を小さい単位で言い表すと考え方が変わる」と本では説明しています。
例えば、
- 退職まであと10年→退職まであと3652日
と言い換えると、急にそれほど先のこととは思えなくなります。
来月いくら使うかより1年後いくら使うか予想する
また、
- 来月はいくら使うか予想する
- 1年後はいくら使うか予想する
では、来月だと実際より少なく見積もってしまいますが、1年後だと正確な数値にずっと近くなります。
人は1年後のことはよく分からないから、見込み違いの余地を織り込んで金額を多めに設定します。そうすると、実際には正確な数値になるそうです。
まとめ、書評
以上、「MIND OVER MONEY 193の心理研究でわかったお金に支配されない13の真実」から学んだことを、
①現金よりクレジットカードの方が多く支払ってしまう
②お買い得が脳をパンクさせる
③お金が貯まる心の持ち方
の3点紹介しました。
僕にとってお金の使い方が変わった最重要な本です。
クレジットカードの方がいくらお得でも、お金のコントロールが難しくなります。不器用な僕にとっては、クレジットカードを固定費以外には使わないが最適解でした。
他にもたくさんの人とお金の関係性を本では紹介しています。
この本を読んで、お金に対する人間の行動心理を理解すれば、確実にマネーリテラシーが上がります。
興味のある方はぜひご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました!
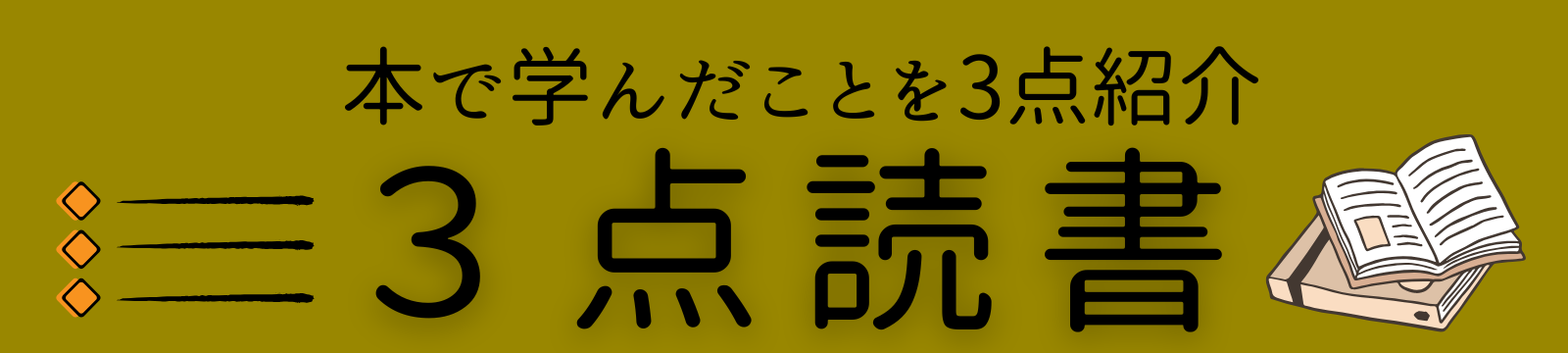

コメント